弊社は民間保険会社の代理店をしております。民間保険には公的保険を補完する趣旨があり、そのため公的保険の情報提供をすることが必要とのことです。これは金融庁の監督指針として明確化されました。 というわけで、公的保険についても少しずつ触れていこうと思います。 なお内容は2022.8.5現在をベースにしています。
■公的保険
▼公的保険と社会保険
どのような違いがあるのでしょうか?
基本的に同義と思っていただいて構わないと思います。
もしかしたら厳密には違うかもしれませんが、一般的に混同されています。社会保険は社会保障制度の内の一つですので、社会保障の枠組みで考える場合に「社会保険」と使われることが多いように感じます。社会保障には、他に生活保護などがあります。
この記事では「公的保険」に統一します。
▼どのような種類があるのか。
まずどのような種類があるのか、そこから始めたいと思います。
それでは公的保険の種類ですが、大きく5つに分けられます。
公的医療保険
公的年金保険
雇用保険
労災保険
公的介護保険
民間保険との比較ですが、金融庁が最近作成したポータルサイトがあります。そこから抜粋します。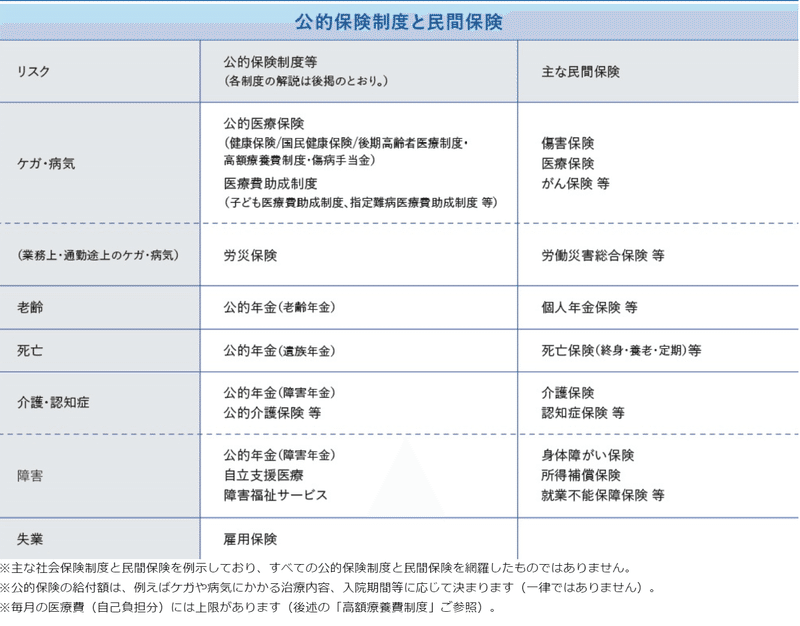 情報提供は義務ではなく必要に応じてということです。けれども個人保険において、確かに何も説明しなくてよいところはないように感じますね。法人保険はまた別ですが。
情報提供は義務ではなく必要に応じてということです。けれども個人保険において、確かに何も説明しなくてよいところはないように感じますね。法人保険はまた別ですが。
▼保険料
1.公的医療保険
・負担率
保険者(保険組合等)によって異なります。保険者は健康保険被保険者証を見て頂くと記載されています。 また介護保険第2号被保険者に該当するかどうかで変わります。公的介護保険料が上乗せされる形です。 一般的には40歳未満は該当せず、40歳以上65歳未満の方が該当になります。(海外勤務や障害手帳を持っているなど例外もあります。)
標準報酬月額の内
第2号被保険者に該当しない 9.81%
第2号被保険者に該当する 11.45%
この金額を事業主と従業員で折半します。給与明細に記載されているのは折半後です。
弊社は東京にあるので、全国健康保険協会(協会けんぽ)の東京支部 令和4年版から抜粋しました。
・保険料支払方法
給与から天引き
口座から引き落とし
納付書支払
クレジットカードやLINE Pay(対応している場合)
2.公的年金保険
・負担額
国民年金は月額16,590円(令和4年度)
厚生年金(国民年金を含む)は標準報酬月額の18.3%
厚生年金は、この金額を事業主と従業員で折半します。給与明細に記載されているのは折半後です。
・保険料支払方法
給与から天引き(第2号被保険者)
納付書支払
口座引落
クレジットカード払(第1号被保険者)
3.雇用保険
・負担率
10月から変わります。(厚生労働省HP)
一般の事業のみ取り上げます。
9月まで 従業員0.3% 事業主0.65%
10月から 従業員0.5% 事業主0.85%
%表記にしました。
・保険料支払方法
給与から天引き
明細を見ると、他の社会保険料や税金と比較されて安く感じます。
4.労災保険と併せて労働保険と呼ばれており、合算して納付します。
4.労災保険
・負担率
事業主負担のみで、従業員負担はありません。
また、保険料率は事業種別によってバラバラです。(厚生労働省HP)
0.25%~0.6%
・保険料支払方法
口振または電子申請
3.雇用保険と併せて労働保険と呼ばれて、合算して納付します。
5.公的介護保険
・負担率
40歳以上65歳未満は、1.64%
65歳以上は、自治体ごとに計算される「基準額」と、「本人・世帯の所得状況」によって決定されます。
弊社所在の千代田区は19,400円~226,800円です。
・保険料支払い方法
40歳以上65歳未満は、公的医療保険に上乗せして支払い。
65歳以上は年金から天引き、口座振替、納付書。
■まとめ
・民間保険は公的保険を補完する趣旨がある。
・大きく分けて5種類ある。
・保険料支払いには、事業主負担・従業員負担・天引き等々パターンがある。
■担当の一言
法人メインである弊社は、公的保険の細かい説明をすることはあまりありませんでした。法人は公的保険の対象とはならないためです。だからこそ民間保険で補完する必要性は高いとも言えます。売り手側の一意見でした。
