倒れてからの日常──脳卒中と“その後の生活”
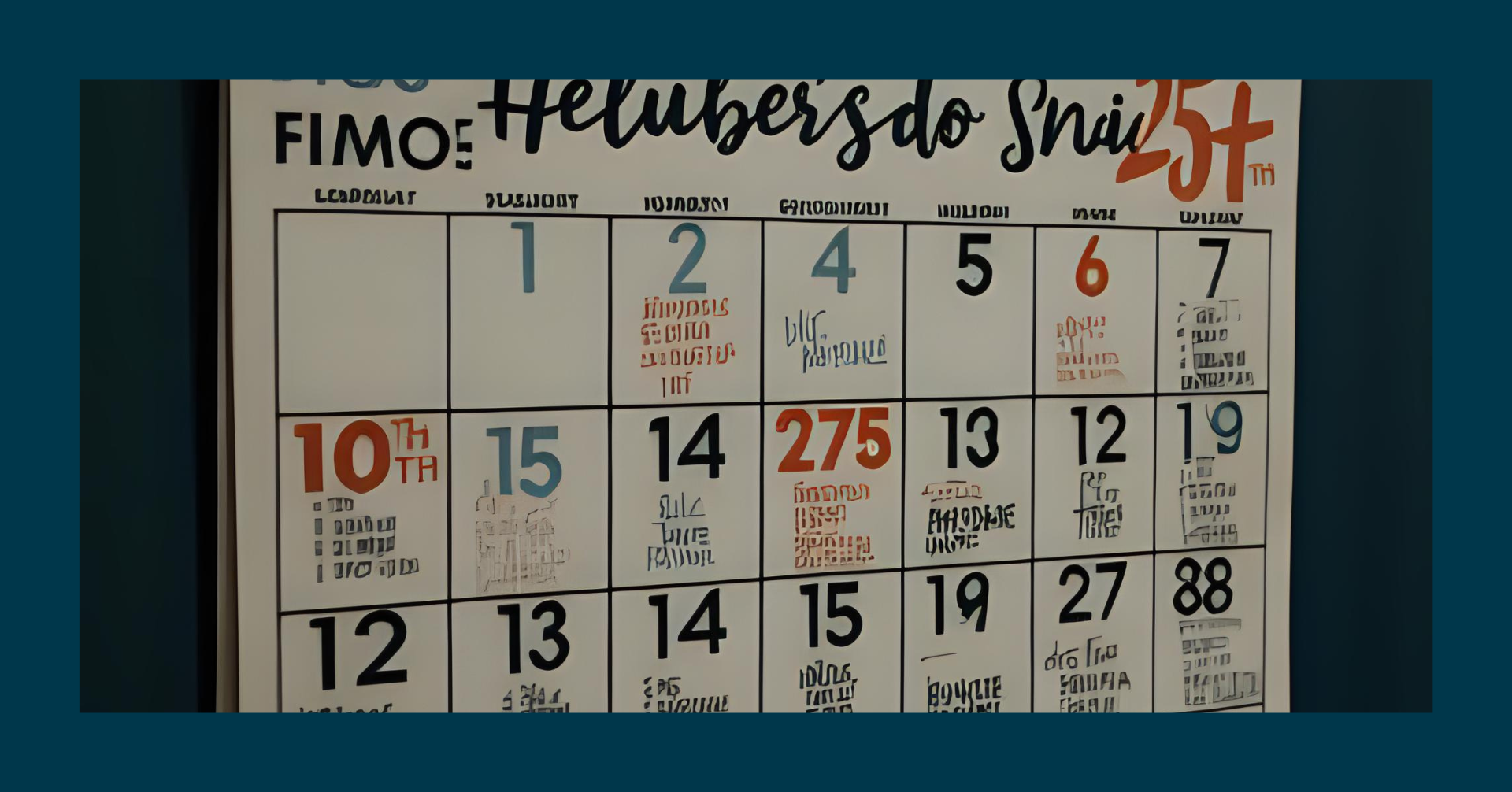
こんにちは、毎年「脂質異常症」と診断され、そろそろ“異常”じゃなくて“仕様”では?と開き直り始めたユナイトnote編集部です。
異常症って強烈ですよね。血液中の脂質の量には自信がありますと言い換えてみようか。
さて、今回は、そんな脂質異常症も関わるとされる「脳卒中」について取り上げます。
慌てず冷静に見ていきましょう。
■ 脳卒中とは?──脳の血管に起こる“突然のトラブル”
脳卒中とは、脳の血管に起こる急性の障害の総称です。
「脳血管疾患」とほぼ同じ意味で使われることもありますが、脳卒中は急性期に限定されることが多いようです。
主な3タイプは以下の通りです:
• 脳梗塞:脳の血管が詰まる
• 脳出血:脳の血管が破れて出血する
• くも膜下出血:脳の表面にあるくも膜下腔で出血(多くは動脈瘤の破裂が原因)
どれも、聞くだけで体がこわばるような名前です。
■ 致死率と死亡数──意外にも「即死ではない」?
「倒れたら終わり」というイメージのある脳卒中ですが、データを見ると少し違った側面が見えてきます。
致死率(急性期)
• 脳梗塞:約10〜15%
• 脳出血:約20〜40%(重症は50%超)
• くも膜下出血:約30〜50%
年間死亡数(日本)
• 脳梗塞:約43,000人
• 脳出血:約22,000人
• くも膜下出血:約9,000人
致死率を下げるカギは、異変にすぐ気づくこと。
以下のような症状は要注意です:
• 顔の片側がゆがむ
• 手足に力が入らない
• ろれつが回らない
• 言葉が出てこない・理解できない
※「政治家の言っていることが理解できない」はおそらく多くの人に共通の症状なのでご安心を。
致死率で比較すると
くも膜下出血 > 脳出血 > 脳梗塞 という順。
「もっと亡くなると思っていた」という方もいるかもしれませんが、生き残った後の生活の支援こそが重要な病気だとも言えます。
■ 脳卒中の後遺症──“命は助かったけど”の現実
脳卒中の恐ろしさは、生存後に残る後遺症の多さと重さにあります。
代表的な後遺症:
• 運動障害:マヒ、歩行困難など
• 高次脳機能障害:記憶力・判断力の低下
• 失語・構音障害:話す、聞く、読む、書く能力の一部が失われる
• 感覚障害:しびれ、知覚異常
• 視野障害:見えない範囲が生じる
• 排泄障害:尿失禁など
症状の程度によっては、身体障害者手帳や障害年金の対象になる場合もあります。
「命は助かったけれど、以前のようには働けない──」
そんな現実があるのが、脳卒中です。
■ 再発リスク──「もう一度」は想像以上に多い
脳卒中は、再発率が高い病気でもあります。
• 5年以内の再発率:約30%
• (参考)心筋梗塞:約10% (根拠がありませんでした。3年で30%ほどというデータもありました。失礼しました。2025/7/29追記)
再発リスクを高める要因:
• 高血圧
• 糖尿病
• 脂質異常症(!)
• 喫煙・飲酒
言い換えると、生活習慣との関係が深い病気でもあるということです。
■ 就業への影響──“いつもの仕事”ができなくなる
脳卒中がもたらすのは、医療的な影響だけではありません。仕事への影響も深刻です。
• 肉体労働系:片麻痺や体力低下により復職が難しいケースも
• ホワイトカラー系:高次脳機能障害・失語などにより、業務遂行に支障が出ることも
• 再発リスクへの配慮:ストレスや長時間労働を避ける必要がある場合も
復職率は調査によって異なりますが、40〜60%程度とされることが多いようです。半数が戻れていません。
「治った=元の仕事に戻れる」わけではない現実も、受け入れなければならないのです。
■ 保険と制度──“もしもの備え”は多層で考える
脳卒中の影響は長期に及ぶため、保険や公的制度による備えが重要です。
【民間保険の備え】
• 医療保険・特定疾病(三大疾病)保険
• 後遺症があれば介護保険・就業不能保険の対象になることも
【公的制度の活用】
• 健康保険(治療費)・高額療養費制度
• 障害年金・介護保険(要介護認定)など
「治療が終わったら、それで終わり」ではありません。
その後の生活をどう支えるかが、制度選びの重要な視点です。
■ まとめ
今回、脳卒中について網羅的に取り上げました。
正直、致死率は私のイメージよりやや低めでした。
ただし、生存後に残る後遺症の深刻さを改めて実感し、背筋が伸びる思いです。
生活・仕事・収入──支えるべきものが多いからこそ、備えは制度だけでなく、周囲の理解や職場の配慮も含めて必要です。
「突然倒れる」は、もはや他人事ではありません。
少しずつでも、自分ごととして備えを始めていきましょう。
お忙しい中、最後までお読みいただきありがとうございました。
※注意点
• 記事内容の正誤に関わらず、読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。
• より正確な内容を知りたい場合は「■参考」などをご覧いただければと思います。
• 本記事は2024年11月時点の情報に基づいています。
• 詳細は税理士や税務署にご確認ください。
■問い合わせ先
• 保険の質問やご相談:お問い合わせフォーム
• Instagram:ユナイト公式アカウント
感想や質問などコメントいただけると嬉しいです。
■参考
▼脳血管疾患の患者数はどれくらい?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター
▼0000198760.pdf 厚生労働省事業場における治療と職業生活の両立支援のための ガイドライン 参考資料 脳卒中に関する留意事項